「やっぱりBYDはやめとけってこと…?」
そんな疑問が浮かんだ瞬間、ネットで検索を始めた方も多いのではないでしょうか。
「BYD 危険性」「BYD 故障率」「BYD 品質 悪い」といった不安をあおるワードが並び、
ついには「BYD 買わない方がいい」という結論にたどり着いてしまう――。
でも、その判断、少しだけ早いかもしれません。
EVにまだ慣れていない日本市場では、BYDのような新興ブランドに対する情報が限られているのが現状です。
「売れない理由」や「安い理由」には、意外と合理的な仕組みがあり、
悪評の多くは誤解や情報不足から生まれているケースも少なくありません。
このページでは、BYDに関する不安の正体を一つずつ丁寧に整理しながら、
「やめとけ」と言われる理由が本当に正しいのかを冷静に見つめ直していきます。
そのうえで、実際に満足しているユーザーの声や、購入前に確認すべきポイントまで、
あなたが後悔しない判断をするために必要な情報をまとめています。
読み終えたとき、「BYDを買うべきか迷っていたけど、自分で納得できた」
そう感じていただけるはずです。ぜひ、最後までご覧ください。
タイトル画像 引用:BYD
記事のポイント!
- BYDが「やめとけ」と言われる背景と実情
- 品質や故障率に関する誤解と事実の違い
- 日本市場での販売状況と拠点拡大の流れ
- 後悔しないための選び方と比較の視点
BYDは本当にやめとけ?不安の正体とその背景

「byd やめ とけ」と検索する方の多くは、
ネットで目にする“悪い評判”や“買って後悔する”といった声に不安を感じているはずです。
確かに、ブランドの知名度やサポート体制、中国車という背景など、
懸念につながる要素がゼロとは言い切れません。
しかし、その一つひとつの「理由」を深掘りしていくと、
誤解や古い情報に基づくものも多く含まれているのが実情です。
まずは、なぜBYDがやめとけと言われるのか、
その“根本的な不安の正体”を見つめ直すことから始めましょう。
- BYDが売れない理由は何ですか?
- BYDの危険性と品質への誤解
- 中国車=低品質という先入観
- BYDは終わりましたか?という噂
- BYDの悪評と信頼性の実態
- EVへの理解不足による「やばい」不安
- なぜ「BYD 買わない人」が一定数いるのか
BYDが売れない理由は何ですか?

✔ 認知度が低く安心感に欠ける
✔ EV市場自体の成長が限定的
✔ ブランド選びで国産が優先されやすい
日本市場でBYDが思うように売れていない背景には、複数の要因が絡んでいます。
まず、多くの日本人にとって「BYD」というブランドはまだまだなじみが薄く、知名度や安心感では国産車や欧州車に劣るのが現状です。これは“知らないものには手を出しづらい”という消費者心理によるものだといえるでしょう。
また、国内のEV市場自体がまだ本格的に拡大していないことも一因です。日本では充電設備の整備が都市部に偏っており、マンション住まいなどではEVを選びにくいという声も多く聞かれます。結果として、せっかくBYDが価格・性能面で優れたモデルを投入していても、その価値が浸透しにくい状況となっています。
さらに、車選びにおいて“信頼感”を重視する日本人の特性上、初めて聞く海外メーカーよりも、馴染みのある国産ブランドを選ぶ傾向があります。これもBYDが苦戦している理由の一つといえるでしょう。
今後、日本市場での販売を本格化させるには、認知度向上とともに、EVインフラや販売店網の拡充が不可欠です。

BYDの危険性と品質への誤解

✔ 中国製=低品質という古いイメージ
✔ 最新モデルは安全基準をクリア済み
✔ 品質面はむしろ急成長している
「BYDは危険」といった印象を持たれることがありますが、それは過去の中国製品に対する先入観によるものが大半です。昔のような品質のばらつきは、現在のBYDにはほとんど見られません。
実際、BYDの車両はヨーロッパを含む複数の地域で厳しい安全基準をクリアしています。衝突安全性や電池の耐久性、ブレーキ性能など、国際的に通用する水準に達しており、日本での販売車種もこれに準拠しています。
中国メーカー=粗悪品という認識は、もはや現代のEV市場では通用しません。スマートフォンや家電と同様に、自動車分野でも「実力ある中国企業」が台頭しています。BYDもその筆頭といえる存在で、テスラに電池を供給している事実からも、技術力の高さがうかがえます。
むしろ、誤解や噂だけで敬遠するのはもったいない時代に入ってきているのではないでしょうか。大切なのは、古いイメージではなく、現行モデルの実力で判断する姿勢です。
中国車=低品質という先入観


✔ 昔の中国製品の印象が残っている
✔ 実際は技術水準が大きく進化
✔ EV分野では世界トップクラスの実力
「中国車は品質が悪い」というイメージは、かつての製品事情を引きずった先入観からきていることが多いです。
2000年代初頭の中国製品には粗悪品も多く、信頼性に欠ける印象が日本市場でも広まりました。
しかし、現在の中国自動車メーカーは大きく変化しています。特にEV技術の分野では、バッテリーやモーター、コネクテッド機能において世界最先端クラスといえる水準に達しています。BYDはその中でも筆頭格であり、世界で最も多くEVを販売する企業の一つです。
テスラにも電池を供給している実績があり、欧州でも高評価を受けています。つまり、「中国=低品質」という図式はすでに過去のものであり、現代のBYD車を正当に評価するには、冷静な情報収集が必要といえるでしょう。
疑念を持つこと自体は当然ですが、時代の変化を受け入れることで選択肢の幅は大きく広がります。
BYDは終わりましたか?という噂

✔「撤退するのでは」との噂がある
✔ 実際には拠点拡大や新車種投入中
✔ 今はむしろ「始まったばかり」の段階
SNSや一部メディアでは「BYDはもう終わった」「すぐ撤退する」といった声も見られますが、その内容は事実とは大きく異なります。
実際のところ、BYDは2023年以降、日本市場での本格展開をスタートさせたばかりです。
現在は都市部を中心にディーラー拠点を増やしながら、DOLPHINやATTO 3などのEV車種を順次投入中です。加えて、2025年以降にはさらなる車種ラインナップの拡充も予定されており、撤退どころか攻勢の真っ最中だといえる状況です。
「終わった」という噂は、EV市場全体の成長の遅さや、一部の販売データだけを見て過剰に不安視したものだと考えられます。
日本のEV市場そのものがまだ発展途上にある今、BYDの評価を決めつけるのは時期尚早です。冷静に情報を集めたうえで判断することが、後悔しない選択につながります。
BYDの悪評と信頼性の実態

✔ 一部の悪評は誤解や古い情報
✔ 信頼性はEV専業メーカーならでは
✔ ネガティブ評価は情報不足が原因
BYDに関しては「悪評が多い」と感じる方も少なくありません。ですが、よく見るとその多くは実際のオーナーの声ではなく、ネット上の噂や古い印象に基づいた情報であるケースが目立ちます。
特に「中国車だから壊れやすい」「信頼性に欠ける」といった声は、過去の製品イメージが先行している場合が多いです。しかし、現在のBYDはEV専業メーカーとして世界的に高いシェアを誇っており、テスラやヒョンデと肩を並べる存在です。部品供給の安定性や電動パワートレインの品質にも定評があります。
また、ネガティブな意見が目立つ理由のひとつに「情報不足」も挙げられます。まだ日本では車種や販売拠点が少ないため、十分な試乗体験やレビューが集まりにくく、結果として不安が先行しやすい傾向があるのです。
ネットの評判だけで判断せず、信頼できる公式情報や実車での体験を元に評価することが大切です。
EVへの理解不足による「やばい」不安


✔ 充電やバッテリーに不安を抱えやすい
✔ EV特有の挙動に慣れが必要
✔ 情報不足が「やばい」と感じさせる
「BYDってやばいって聞いたけど?」という声の多くは、実はEV自体に対する不安が影響しています。
ガソリン車とは異なる操作感や維持方法に慣れていない人にとって、EVは未知の存在になりやすいからです。
例えば、「充電時間が長そう」「電池がすぐ劣化するのでは」といった懸念はよくある誤解です。実際には、最新のBYD車は急速充電に対応しており、バッテリーの劣化対策もしっかり講じられています。
また、回生ブレーキによる減速感や、エンジン音のない静かな加速も、初めてのEVユーザーには違和感につながりやすい部分です。これが「運転が難しそう」「扱いづらい」という印象を生む一因となっています。
これらの疑問は、実際に試乗してみることでほとんど解消されるケースが多いです。知識と体験の両方があれば、「やばい」と感じるどころか、「思ったより便利」と感じる方も増えるはずです。
なぜ「BYD 買わない人」が一定数いるのか

✔ ブランド認知が低く安心感に欠ける
✔ アフターサポート体制に不安が残る
✔ 国産車との価格差が小さく感じる
BYDをあえて選ばない層が一定数いるのは、明確な理由があります。
その中でも大きいのが「ブランドへの信頼感」の不足です。日本国内での知名度がまだ低いため、初めて聞くブランドの車を購入することに抵抗を感じる人は少なくありません。
もう一つの理由が、アフターサービスの体制です。大手国産メーカーに比べてディーラー網が限られており、整備や保証に対する不安を抱く声も見受けられます。特に地方在住者にとっては、万が一の対応が気になるポイントになるでしょう。
さらに、車両価格と装備のバランスに対して「それなら国産のハイブリッド車でも良いのでは?」と比較してしまう人もいます。EVとしての優位性をしっかり理解しなければ、価格だけでは魅力を伝えにくい現状もあるのです。
このように、選ばないのは「悪いから」ではなく、「まだ不安があるから」といえるでしょう。

愛車の乗り換えを考えている方へ
今のクルマ、予想以上の価格で売れるかもしれません。
私も実際に【カービューの一括査定】を試してみて、その結果に正直驚きました。
申し込みは1分、もちろん完全無料。
気になる方は、今のうちに愛車の価値をチェックしてみるのがおすすめです。
※すでにご存じの方や、該当しない方はこの案内はスルーしてください。
BYDはやめとけじゃない!後悔しない選び方と判断軸

「やめとけ」という意見だけを鵜呑みにしてしまうと、
本来なら得られるはずだった価値を見逃してしまうかもしれません。
実際、BYDを選んで満足しているユーザーも存在し、
使い方やライフスタイルに合えば“アリ”な選択肢であることも事実です。
大切なのは、「自分に合うかどうか」を冷静に見極めること。
このパートでは、試乗・保証・充電環境など、
後悔しないために押さえておきたい判断ポイントを解説していきます。
あなたのEV選びに役立つヒントがきっと見つかるはずです。
- BYDを買う人いるの?満足層の特徴
- BYDのコスパと安い理由の裏側
- BYDの故障率は本当に高いのか?
- アフターサポート体制の現状と注意点
- BYDの弱点はどこですか?ライフスタイルとの相性
- BYDは日本からいつ撤退するの?という疑問
- 後悔しないための買い方と比較ポイント
BYDを買う人いるの?満足層の特徴

✔ EVの走行性能や静粛性を評価
✔ 車両価格と装備のバランスに満足
✔ セカンドカーや街乗り用として選ばれる傾向
BYD車を実際に購入し、満足しているユーザーも確実に存在します。
そういった層に共通するのは、「EVに理解があり、価格と性能のバランスを重視する」という姿勢です。
たとえば、ATTO 3やDOLPHINのようなモデルは、電動ならではのスムーズな加速と静音性が魅力です。走り出しの滑らかさや室内の静かさは、ガソリン車では味わえない体験を提供してくれます。
また、価格帯に対する装備の充実ぶりもポイントです。大型ディスプレイや先進的なインテリアデザインに満足する声が多く、コスパを重視する人に選ばれやすい傾向があります。
用途としては、メインカーよりもセカンドカーや街乗り用として選ばれることが多く、EV初心者にとっても入り口として適しています。
「新しいものを取り入れる感覚」を持ったユーザーが、BYDの価値を早くから認めているのです。
BYDのコスパと安い理由の裏側


✔ 設備投資と自社一貫生産でコスト削減
✔ 高額なブランド広告を抑えている
✔ 本体価格の割に装備は充実している
「どうしてこんなに安いの?」と驚かれることもあるBYDの車ですが、その理由は単なる低価格戦略ではありません。
実は、製造体制の合理化とマーケティング手法が大きく関係しています。
まず、BYDは電池から車体までを自社で一貫生産する体制を整えており、外部に依存するコストがほとんどありません。
バッテリー製造でも高いシェアを誇っており、他メーカーが苦労する部分を内部でまかなうことで、コストダウンが実現できているのです。
また、トヨタやホンダのような大規模なTVCMや長期キャンペーンではなく、WEBやSNS中心のプロモーションを行っている点も価格に影響しています。ブランドイメージよりも“モノの中身”で勝負しているのが特徴です。
加えて、価格帯の割に先進装備が豊富で、電動スライドディスプレイなど個性的な機能も魅力のひとつ。
コスパの良さは単に「安いから」ではなく、「高品質を手頃に提供する工夫の積み重ね」なのです。
BYDの故障率は本当に高いのか?

✔ 実際の故障率は高くないとの報告
✔ バッテリーと電動システムに定評あり
✔ 故障不安は情報不足から来るケースも
「BYDって壊れやすいって聞いたけど……」という疑問を抱く人は少なくありません。
ただ、現時点での実車データや第三者評価を見る限り、故障率が特別高いという事実は確認されていません。
BYDはバッテリー技術において世界的な評価を得ており、自社で生産しているリン酸鉄リチウム電池(LFP)は、発火リスクが少なく長寿命なのが特徴です。これはテスラ車の一部にも採用されるほど信頼性の高い構造です。
また、EVに多い「モーターやインバーターの故障」についても、BYDでは耐久性を重視した設計がされており、中国国内での過走行レビューでも良好な結果が多く報告されています。
ただし、日本ではまだ流通数が少なく、整備体制もこれから拡大中の段階です。そのため、「不具合=大問題」と感じやすくなる傾向があります。
大事なのは、故障率という“数字”ではなく、どんな対応体制が整っているかまで確認すること。購入時には保証内容やサポートの範囲をしっかりチェックしておくことが重要です。
アフターサポート体制の現状と注意点


✔ 全国に整備網がまだ広がっていない
✔ 故障時の対応スピードに差がある
✔ 購入前に保証や店舗の確認が重要
BYDを選ぶうえで気になるポイントの一つが、アフターサポート体制です。
現在、日本での販売網は都市部を中心に整備が進んでいますが、地方ではまだ拠点が限られており、対応のスピードやカバー範囲に不安を感じる方もいるでしょう。
特に、急な不具合や事故対応が必要になったとき、最寄りのサービスステーションが遠いと不便さを感じる可能性があります。代車手配や部品取り寄せに時間がかかるケースも想定されます。
また、BYD独自のパーツや電子制御系統は、一般の整備工場では対応が難しい場面もあります。これにより、トヨタや日産のような全国対応の整備体制と比べると、サポート面における差を感じることもあるでしょう。
購入を検討する際は、最寄りの販売店やサービス対応エリアを事前に確認しておくことが重要です。加えて、延長保証の有無や対応内容についても、しっかりチェックしておきたいところです。
BYDの弱点はどこですか?ライフスタイルとの相性


✔ 長距離走行や地方での充電環境に課題
✔ インテリアの好みは分かれやすい
✔ 国産車ほどの細やかさを求める人には不向き
BYD車の魅力は多いものの、ライフスタイルによっては「合わない」と感じる場面もあります。
特に注意したいのは、長距離移動が多い人や充電インフラが乏しい地域に住んでいる場合です。
都市部では充電ステーションの設置が進んでいる一方で、郊外や山間部では依然として不足しているエリアもあります。自宅充電環境がない場合、日々の運用がストレスになる可能性も否定できません。
また、BYD車の内装は先進的で個性的なデザインが特徴ですが、その分「好みが分かれる」という側面もあります。画面の多用やライトの演出が苦手な方には、やや派手に感じるかもしれません。
さらに、ドアの閉まり方やスイッチの質感など、日本車が得意とする“細やかな仕上げ”を重視する方には、やや物足りなさを感じることもあるでしょう。
自分の生活スタイルや好みと照らし合わせて、本当にフィットするかどうかを見極めることが、後悔のない選択につながります。
BYDは日本からいつ撤退するの?という疑問

✔ 現在はむしろ本格参入の初期段階
✔ 撤退の公式発表や兆候は一切なし
✔ 今後の成長戦略にも注目が集まる
一部のSNSや口コミで「BYDは日本から撤退するのでは?」という声が見られます。
しかし、現状としてそのような兆しは一切なく、むしろ真逆の動きが進んでいます。
BYDは2023年に日本市場への本格参入を開始し、すでにDOLPHINやATTO 3など複数のEVを販売中。
さらに、全国の主要都市に正規ディーラーを順次展開しており、2025年には20拠点以上を目指す計画も発表されています。
撤退の噂は、おそらくEV市場全体の成長スピードが遅いことや、中国メーカーへの不信感からくるものだと考えられます。
ただし、BYDは世界的に見てもEVシェアトップクラスのメーカーであり、日本市場もその戦略の一環として重視されているのが現実です。
将来を見据えると、「撤退」ではなく「拡大」をキーワードに注目するのが妥当といえるでしょう。
後悔しないための買い方と比較ポイント


✔ 試乗と充電環境の確認が必須
✔ 保証や維持費の把握も重要
✔ 国産EVやリースとの比較も有効
BYDを検討するうえで、購入時に後悔しないための準備は欠かせません。
特に重要なのが「実車に触れること」と「使用環境との相性確認」です。
まず、EVに不慣れな方は、必ず試乗を行うことをおすすめします。加速感や静粛性は魅力ですが、独特の回生ブレーキなど運転感覚にクセを感じる人もいます。体験してみて初めて、自分に合うかどうかが分かるはずです。
次に、自宅や近隣の充電インフラをチェックすることも大切です。戸建てなら問題ありませんが、マンションや地方エリアでは、使い勝手に差が出やすいポイントとなります。
さらに、保証内容・メンテナンス費用・リセールバリューといった“長期的コスト”にも注目を。
購入ではなくカーリースやサブスクという手段も選択肢に入れると、失敗のリスクを抑えやすくなります。
「価格が安いから」だけで選ぶのではなく、ライフスタイル・予算・運用環境を総合的に考えることが、満足度の高いEV選びにつながります。
私が最近ディーラーで査定してもらったとき、
金額があまりに安くて正直ショックでした…。
そんな時に知り合いに教えてもらったのが、無料の一括査定サービス。
実際に使ってみたら、思ったより高くてちょっと得した気分でした。
🚗 無料で5社まとめて査定するなら → カービュー公式サイト
無料なので、同じ悩みの方は試してみる価値あり!
※すでに知っている方や、関係ない方はスルーしてください。
BYDは本当にやめとけ?後悔しないための注意点と選び方を解説のまとめ
記事のポイントをまとめてます。
- 日本ではBYDのブランド認知がまだ低い
- 知名度の低さが安心感の欠如につながっている
- 日本のEV市場自体がまだ成熟していない
- 国産車を優先する傾向が根強い
- 「中国製=危険」という古い印象が残っている
- 現在のBYD車は国際的な安全基準を満たしている
- 中国EVメーカー全体が技術進化している
- ネット上の悪評は古い情報や誤解に基づく場合が多い
- EVに対する情報不足が「やばい」と感じさせている
- 回生ブレーキや静音性に慣れが必要な場面がある
- 地方では充電設備や整備拠点が少ないことがある
- BYDは現在、日本でディーラー拡大中である
- 撤退の兆候はなく、今は展開フェーズの初期段階
- アフターサービス体制は都市部中心で課題もある
- 内装デザインが好みによって評価が分かれる
- 細部の仕上がりに国産車との違いを感じる人もいる
- 自宅充電環境がないとEV運用が難しいケースもある
- 試乗や保証内容の確認は購入前に必須である
- BYDの価格は一貫生産体制でコストを抑えた結果である
- 装備の充実度と価格のバランスがコスパの評価につながっている
- 故障率は特別高くなく、誤解による不安が多い
- バッテリーはLFP型で安全性と耐久性に優れている
- セカンドカーや街乗り用として選ばれることが多い
- リースやサブスク活用で失敗リスクを減らせる
- 購入しない人は「不安だから」という理由が大半である
- 正しい情報を得て判断すれば後悔しにくい選択ができる

管理人の車好きからの心からの一言
こんにちは、車好きの管理人です。最後まで読んでいただきありがとうございます。
「BYDはやめとけ」といった声があるのは事実ですが、調べてみると誤解や情報不足によるものも少なくありません。たとえば昔の中国製品=品質が悪いという印象は、今のEV市場では必ずしも当てはまらないと感じています。実際、BYDはテスラにも電池を供給するほどの技術を持っていますし、日本でも徐々に実績を積み重ねてきています。
車選びって、ラーメン屋さんを選ぶのと少し似ていると思うんです。好みの味や雰囲気は人それぞれで、「行ってみないとわからない」部分もある。BYDもまさにそのタイプ。気になるなら、まずは試乗してみる。実物に触れて感じることで、ネットの評判とは違った一面が見えてくるかもしれません。
少しでも気になるなら、先入観にとらわれず、自分の目と体で確かめてみるのがおすすめです。
あなたにぴったりの「BYDの魅力」を見つけてみてください!
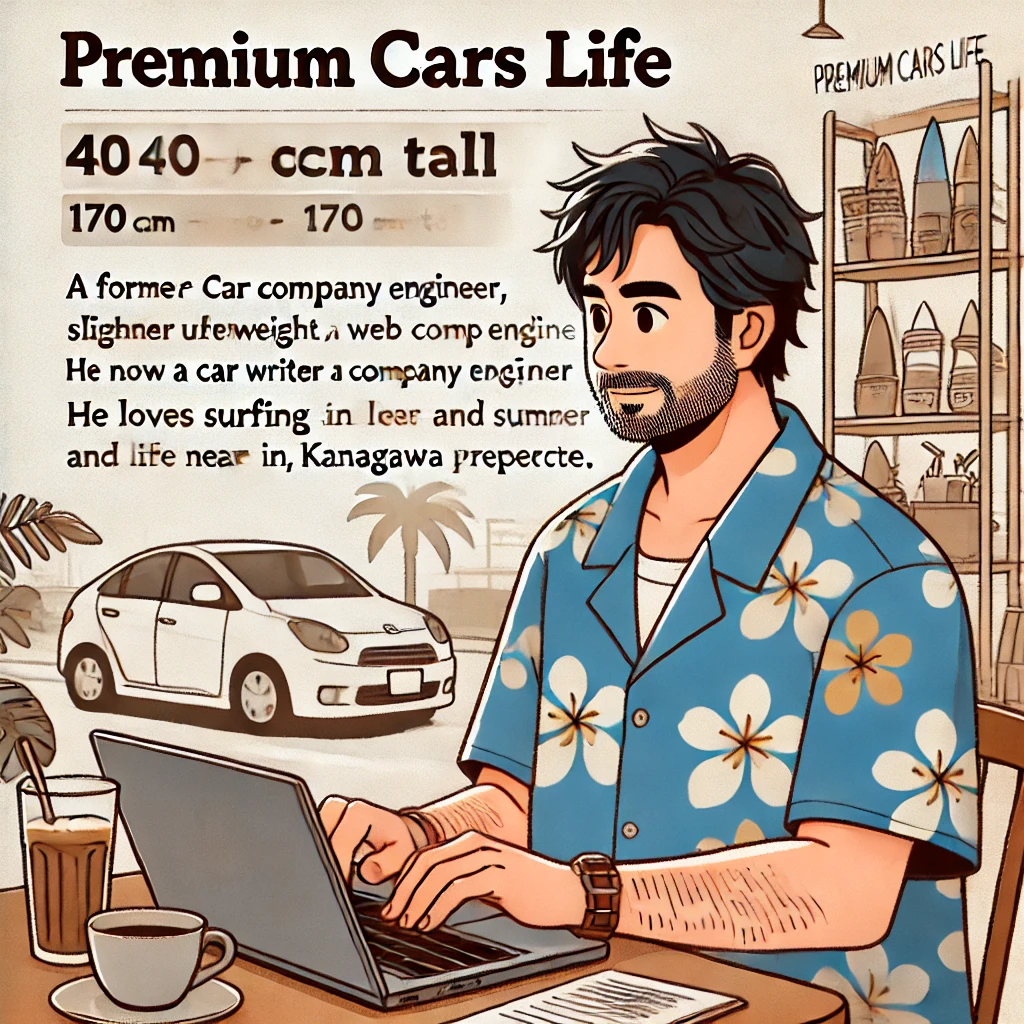
関連記事・参照リンク
・【公式】BYD AUTO JAPAN
・TOYOTA bZシリーズ第2弾「TOYOTA bZ3」を中国で発表
