電気自動車が注目される今、「BYDって実際どうなの?買う人いるの?」と気になって調べている方も多いのではないでしょうか。
長澤まさみさんのCMで一気に知名度は上がったものの、「がっかりだった」「やめとけという声もある」と聞くと、不安になるのも無理はありません。
実際、BYDは世界ではEVシェアトップクラスでありながら、日本では「売れない理由」や「日本撤退の噂」がつきまとうなど、評価が真っ二つに分かれています。
ですが、販売台数やユーザーの口コミ、バッテリーの耐久性やサポート体制の実態を整理してみると、「なぜそう言われるのか」「どんな人に向いているのか」が見えてきます。
本記事では以下のような視点から、BYDの現状を徹底的に解説します。
- BYDの売れ行きと買う人の特徴
- 「売れない理由」とその裏側にある課題
- 実際の故障率やバッテリー性能
- 長澤まさみ起用CMの効果と限界
「byd 買う人いるの?」と疑問を抱えた今こそ、購入前に知っておくべき情報をまとめてチェックしてみてください。
あなたの判断にきっと役立つはずです。
タイトル画像 引用:BYD
記事のポイント!
- 日本市場でのBYDの販売台数と現状の立ち位置
- BYDを実際に購入している層の特徴と選ばれる理由
- 売れにくいとされる要因や故障率、安全性の実態
- 今後の販売戦略や、日本市場での可能性と課題
BYDは買う人いるの?日本での売れ行きと販売戦略

BYDは世界的なEVメーカーとして注目を集めていますが、
「日本で本当に買う人いるの?」という声も少なくありません。
たしかに販売台数を見ると、他国と比べて日本では控えめな印象です。
では、その理由は単に知名度の問題なのでしょうか?
この章では、BYDの日本における実際の売れ行きや
販売戦略の動きをデータとともに解説します。
EV市場の未来を左右する「今の数字」と「これからの動き」を
知ることで、より現実的な視点で判断ができるようになるはずです。
- BYDは日本で売れているのか?2024年の販売台数と市場シェアの現状
- BYDの車は誰が買う?主な購入層とターゲット層の特徴
- 長澤まさみのCMやマーケティングは効果的か?ブランドイメージと購買意欲
- BYDとトヨタの関係性:協力と競争の行方は?
- 日本のEV市場の現状とBYDのシェア拡大戦略
- ユーザーの口コミと実体験:BYD車のメリット・デメリット
- BYDの販売戦略と今後の展望:2025年に向けた動きと新モデル情報
BYDは日本で売れているのか?2024年の販売台数と市場シェアの現状

✔ 日本での販売台数はまだ少なめ
✔ 市場シェアは1%未満にとどまる
✔ 成長傾向はあるが課題も多い
2024年現在、BYDの日本市場での存在感はまだ限定的です。
上半期の販売台数は約1,000台、通年では2,200台を超える見込みとされていますが、これは全体のEV市場において0.9%のシェアにとどまります。
たしかに前年比で58%の成長という数字は明るい材料ですが、日本の新車市場全体を考えると、まだ「目立って売れている」とは言えない状況です。
その一方で、世界ではEV販売台数でトップを争うBYDが、なぜ日本では伸び悩んでいるのか。その要因には国産メーカーの圧倒的な信頼感や、EVインフラの未整備など複数の壁があると考えられます。
今後、販売拠点の拡充やラインアップの増加によってシェアを伸ばせるかがカギ。
「買う人いるの?」という声が消える日は、まだもう少し先かもしれません。
BYDの車は誰が買う?主な購入層とターゲット層の特徴

✔ 購入者は価格重視のEV初心者が多い
✔ 環境意識の高い家庭ユーザーも注目
✔ 在日中国人・企業からの購入もある
BYDのEVを選ぶ日本の購入者には、いくつかの明確な傾向があります。
まず多いのが、「EVに乗ってみたいけど高額な車は避けたい」という価格重視のエントリーユーザーです。
また、自宅に太陽光発電設備を備えた家庭や、環境意識の高い層も少なくありません。
BYDの車はブレードバッテリーによる長寿命と安全性をうたっており、エコ志向のライフスタイルと相性が良いといえるでしょう。
さらに、在日中国人や中国系企業が購入しているケースも目立ちます。
母国でのブランド認知や実績があるため、安心して選べるという心理が働いていると考えられます。
「誰が買うの?」という疑問には、こうした特定のニーズ層が答えになります。
ただし、これら以外の広範なユーザーに浸透していくには、もう一段の認知度アップとサポート体制の整備が求められるでしょう。
長澤まさみのCMやマーケティングは効果的か?ブランドイメージと購買意欲

✔ CM放映後、来店者数が大幅に増加
✔ ターゲット層への認知拡大には一定の成果
✔ ただし購買意欲への直結には課題も残る
BYDは日本市場への本格参入に合わせ、人気女優・長澤まさみさんを起用したテレビCMを展開しました。
親しみやすく好感度の高いイメージが、EVに対する敷居の高さを和らげる狙いです。
事実、CM放映直後には一部ディーラーで来店者数が約86%増というデータもあり、ブランド認知の面では大きな成果を上げました。
しかし、実際の販売台数や成約率においては劇的な伸びは見られていません。
「知られること」と「買われること」の間には、信頼性・価格・インフラといった別次元の課題が横たわっています。
CM戦略は確かにインパクトを与えましたが、「認知度アップ=売上増加」とは限らないのが自動車業界のリアルです。
次の一手として、試乗体験やSNS活用など“体感ベース”のマーケティングも必要になりそうです。
BYDとトヨタの関係性:協力と競争の行方は?


✔ 両社は電動化で技術提携している
✔ トヨタのbZシリーズにBYD技術が活用
✔ 市場では協力と競合の両面が共存している
BYDとトヨタは、単なるライバル関係ではありません。
BYDとトヨタは、単なるライバル関係ではありません。
実は電動化領域において技術提携を行っており、2020年には共同出資で「BYDトヨタEVテクノロジー」を設立しています。
注目すべきは、トヨタが中国市場向けに展開しているBZ3セダンの開発に、BYDのバッテリーやモーター技術が使われている点です。
これにより、トヨタは現地ニーズに合ったEVを効率的に供給可能となりました。
一方で、日本国内では両社がEV市場で直接競合する局面も増えてきました。
特に価格帯やエントリーモデルのEVにおいては、BYDのコスト競争力がトヨタを脅かす存在にもなりつつあります。
「協力か、競争か?」という問いに対し、今のところ両立が進んでいる状況です。
今後も、グローバル市場の動向によってこの関係がどちらに傾くかは注目に値します。
| 全長 | 4,725mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,835mm |
| 全高 | 1,475mm |
| ホイールベース | 2,880mm |
| Cd値 | 0.218 |
| 乗車人数 | 5 |
| 電池種類 | リチウムイオン電池(正極にLFPを採用) |
日本のEV市場の現状とBYDのシェア拡大戦略

✔ 日本のEV普及率は依然として低水準
✔ 国産勢が強く、外資メーカーは苦戦中
✔ BYDは価格と技術でシェア拡大を狙う
現在、日本のEV市場は全体の新車販売台数に占める割合が2〜3%程度と、世界と比べて低い水準にあります。
その要因には、充電インフラの不足や価格帯の高さ、走行距離に対する不安などが挙げられます。
この市場で圧倒的な存在感を持つのがトヨタや日産などの国産メーカーです。
一方で、外資系EVメーカーの多くは“選ばれる理由”を明確に打ち出せず、苦戦が続いています。
BYDはこの状況を逆手に取り、「価格と装備のバランス」「長寿命バッテリー」など、実利に訴える戦略でシェアを拡大しようとしています。
2025年には販売網を100店舗規模に広げる計画も進行中です。
日本のEV普及率が今後どう変わっていくのか、そしてBYDがどこまで食い込めるのか。
それぞれの動きが重なり始めるタイミングに注目が集まります。
ユーザーの口コミと実体験:BYD車のメリット・デメリット

✔ コスパと静粛性の評価が高い
✔ 内装やソフト面に課題もあり
✔ サポート体制への不安の声も
実際にBYD車に乗っているユーザーの声からは、いくつかの傾向が見えてきます。
まず多くの人が評価しているのが、コストパフォーマンスと走行時の静かさです。
同価格帯のEVと比べても装備が充実しており、都市部での走行には十分という意見が目立ちます。
一方で課題として指摘されるのが、内装の質感やソフトウェアの使い勝手です。
ディスプレイの日本語対応やナビ機能の使いづらさなどが、改善要望として挙げられています。
さらに、アフターサービス体制の薄さも懸念点の一つです。
ディーラーが少ないため、修理や点検に不安を感じているユーザーも少なくありません。
ユーザーのリアルな声を知ることで、購入前の検討材料になります。
どんな車にも一長一短があるからこそ、口コミから“自分に合うか”を見極めていくことが大切です。
BYDの販売戦略と今後の展望:2025年に向けた動きと新モデル情報


✔ 2025年までに販売店を全国100拠点へ拡大
✔ 新モデル投入で選択肢の幅を広げている
✔ サポート体制強化も販売戦略の柱になる
BYDは2025年に向け、日本での販売体制を着実に拡充しています。
現在は都市部中心の販売網を、今後2年間で全国100拠点規模に広げる計画が進行中です。
あわせて新型車の投入も加速しており、すでに「ATTO 3」「DOLPHIN」「SEAL」といった個性的なEVを展開。
さらに日本のニーズに合わせた小型EVの導入も検討されており、選べるラインアップの広がりが期待されています。
加えて、サポート体制の整備も重要な柱です。
修理やメンテナンス面での不安を払拭するため、正規ディーラーでの技術研修や部品供給網の強化が図られています。
価格の魅力だけでは勝ち残れない日本市場で、どこまで“安心して選べるブランド”へ進化できるか。
2025年は、BYDにとって大きな転換点となるでしょう。
愛車の乗り換えを考えている方へ
今のクルマ、予想以上の価格で売れるかもしれません。
私も実際に【カービューの一括査定】を試してみて、その結果に正直驚きました。
申し込みは1分、もちろん完全無料。
気になる方は、今のうちに愛車の価値をチェックしてみるのがおすすめです。
※すでにご存じの方や、該当しない方はこの案内はスルーしてください。
BYDを買う人いるの?購入を迷う理由と将来性を検証

価格の安さや環境性能に惹かれる一方で、
「本当に買って大丈夫なのか?」と迷う人も多いBYDのEV。
特に「byd 買う人いるの」という検索には、
ブランド信頼性やサポート面への不安が込められているようです。
この章では、そうした購入をためらう理由を整理しながら、
今後の成長性や改善への動きにも触れていきます。
どんな選択肢にもメリットとリスクはあります。
その両面を知ったうえで、自分に合った選び方を見つけていきましょう。
- BYDを買う人いるの?購入を迷う理由と将来性を検証
- なぜBYDは日本で売れにくいのか?売れない理由と背景
- BYDの故障率やバッテリーの耐久性はどうか?実際の評判と安全性の評価
- BYDのバッテリーは何年乗れる?耐久性と長期使用の実態
- 日本撤退の可能性は?市場からの退出や今後の展望について
- なぜBYDは売れないと感じるのか?消費者の声と市場の反応
- BYDの充電インフラとアフターサービスの課題
- BYDは買わない方がいいのか?購入検討者へのアドバイス
- BYDは本当に買う人いるの?売れない理由と評判の真相とは!?のまとめ
なぜBYDは日本で売れにくいのか?売れない理由と背景

✔ ブランドの信頼性が日本ではまだ低い
✔ 充電設備の不足がEV普及の足かせに
✔ 中国製品への先入観が根強く残っている
BYDのEVは世界市場では高い実績を誇る一方、日本ではまだ「売れている」とは言い難い状況です。
その最大の要因は、ブランドに対する信頼感の薄さです。
長年、トヨタやホンダが築いてきた安心感に比べ、BYDは新参者として警戒されがちです。
また、日本のEVインフラ整備が遅れている点も販売のネックとなっています。
特にマンション住まいでは自宅充電が難しく、EV購入に踏み切れない層が多いのが現実です。
さらに「中国製=不安」という固定観念も、購買の障害となっています。
品質への評価は上がりつつあるものの、“印象”の壁は簡単に越えられません。
これらの課題を一つずつ解消できるかどうかが、今後の普及スピードを大きく左右していくでしょう。
“安くて良い”だけでは、日本のドライバーの心は動かせないのです。
BYDの故障率やバッテリーの耐久性はどうか?実際の評判と安全性の評価

✔ 故障率はEV全体と同程度の水準
✔ ブレードバッテリーが高い耐熱性を持つ
✔ ソフト面の不具合や初期ロットに注意
BYDの故障率は、「中国製だから壊れやすい」といったイメージとは裏腹に、他のEVメーカーと大きな差はありません。
とくに駆動系やバッテリー部分のトラブルは少なく、一定の信頼性を保っています。
注目すべきは「ブレードバッテリー」の安全性です。
釘刺しテストや高温試験においても発火リスクが極めて低く、世界的にも高評価を得ています。
この構造により、万が一の衝突や異常発熱時にも安定した性能を発揮します。
一方で、ユーザーの口コミではディスプレイやナビの不具合、スマートキーの作動トラブルなど、ソフトウェア系の初期不良が指摘されることもあります。
とくに日本市場に最適化された調整がやや甘いと感じられる部分は、今後の改善が求められるでしょう。
機械的な信頼性は高まっていますが、使い勝手や細かい部分での不安が完全に解消されているとはいえません。
購入前には細かい機能面のチェックも大切です。
BYDのバッテリーは何年乗れる?耐久性と長期使用の実態

✔ 8年・15万キロの公式保証がある
✔ 10年後でも90%以上の容量維持試験あり
✔ 適切な充電環境で長寿命が期待できる
BYDのEVに搭載されるバッテリーは、公式に8年または15万kmの保証が付帯しています。
これは日常使用において十分な期間であり、バッテリーの品質への自信が伺える内容です。
さらに、社内試験では10年使用後でもバッテリー容量の90%を維持するというデータも公開されています。
この性能を支えるのが、熱に強いリン酸鉄リチウム系の「ブレードバッテリー」です。
従来のリチウム電池よりも劣化が遅く、極端な充放電や高温環境でも安定した出力を保ちます。
ただし、どんなバッテリーでも使い方によって寿命は左右されます。
急速充電ばかりを繰り返したり、極端に寒暖差のある地域で放置するなどの使い方は劣化を早める原因となります。
バッテリー性能に関しては業界トップクラスの評価を得ているBYD。
適切な使い方と環境が整っていれば、10年以上の使用も視野に入る性能といえるでしょう。
日本撤退の可能性は?市場からの退出や今後の展望について


✔ 撤退の公式発表は現時点でない
✔ 今後の展開に意欲的な姿勢を示している
✔ 市場次第では戦略転換の可能性もあり
BYDが日本市場から撤退するのではないかという声が一部で聞かれますが、2025年時点で公式な撤退発表は一切ありません。
むしろ、販売拠点の拡大や新車種の投入を通じて、市場シェアの獲得に前向きな姿勢を見せています。
たとえば、全国100店舗体制を目指すディーラー展開や、日本向け小型EVの投入計画などは、“長期戦略”を前提とした動きです。
こうした計画は、短期的な売れ行きの鈍化では崩れにくいといえるでしょう。
ただし、EV市場はインフラや政策動向に左右されやすいジャンルでもあります。
もし想定よりも日本での普及が進まなければ、中長期的には縮小や撤退の選択肢が出てくる可能性もゼロではありません。
今のところは撤退どころか“攻め”の姿勢。
ただ、市場の空気感次第で方向転換もあり得る、そんな段階にあると捉えるのが現実的です。
なぜBYDは売れないと感じるのか?消費者の声と市場の反応

✔ 信頼性とブランド力が課題になっている
✔ デザインや価格帯に抵抗を感じる声も
✔ 購入後のサポート面に不安を抱く層が多い
「BYDはなぜ売れないのか?」という問いには、消費者側の心理的な抵抗感が色濃く影響していると見られます。
日本ではトヨタやホンダといった国内ブランドへの信頼が厚く、新興ブランドへの“様子見”ムードが強いのが現状です。
とくに目立つ声が、「聞き慣れないブランドに数百万円は出しづらい」というもの。
価格帯自体は競合より安価な場合もありますが、その分信頼性やサポート面に不安を感じやすいのです。
さらに、デザインの好みや車内の質感といった“感覚的な部分”でも、日本人の価値観にフィットしきれていない面があるといえるでしょう。
加えて、「どこで修理できるのか」「部品はすぐ届くのか」といった購入後の不安も販売のブレーキになっています。
新しいものが浸透するには時間がかかるもの。
BYDがこの“壁”をどう乗り越えていくかが、日本で成功する鍵を握っています。

BYDの充電インフラとアフターサービスの課題

✔ 自宅充電環境が整っていない人は不便
✔ 公共充電スポットが少なく不安材料
✔ アフターサービス体制は発展途上
BYDのEVは価格や性能に魅力がありますが、使い続けるうえで重要になるのが「充電」と「サポート体制」です。
まず充電インフラの面では、日本全体でEV対応の駐車場や充電器の普及がまだ進んでいないのが現実です。
とくにマンションや集合住宅に住んでいる人は、自宅での充電が難しく、外出先の充電器に依存する生活を強いられる可能性があります。
ただでさえEV全体の充電網が不十分な中で、BYDはまだ専用のネットワークを築けていない状態です。
アフターサービスについても、ディーラー網の整備が進行中であり、現時点では地方での修理対応や部品調達に時間がかかるケースも報告されています。
一部のユーザーからは「問い合わせへのレスポンスが遅い」といった声も見られます。
安心して使い続けるためには、今後どれだけ“身近な存在”として定着できるかがカギになります。
BYDは買わない方がいいのか?購入検討者へのアドバイス

✔ 初EVとしてはコスパの高い選択肢
✔ 充電やサービス面に課題は残る
✔ 買うか迷うならまずは試乗と比較を
「BYDってやめといたほうがいい?」と悩む人は少なくありません。
確かに、信頼性・インフラ・ブランド力の点で、トヨタや日産といった国産勢に比べて不安があるのは事実です。
一方で、BYDは価格と性能のバランスが取れたEVを提供しており、「初めてのEV」や「コスパ重視のセカンドカー」としては選択肢になり得ます。
とくに自宅に充電設備があり、街乗りメインの用途なら実用性は十分です。
大切なのは、「自分の生活スタイルに合っているか?」をしっかり見極めること。
そのためには、試乗や他社EVとの比較、ディーラーでの相談が不可欠です。
買う前にできることを丁寧に積み重ねれば、後悔のない選択ができます。
「安いから」「新しいから」だけで決めず、自分にとっての“最適なEV”かどうかを冷静に判断してみてください。
私が最近ディーラーで査定してもらったとき、
金額があまりに安くて正直ショックでした…。
そんな時に知り合いに教えてもらったのが、無料の一括査定サービス。
実際に使ってみたら、思ったより高くてちょっと得した気分でした。
🚗 無料で5社まとめて査定するなら → カービュー公式サイト
無料なので、同じ悩みの方は試してみる価値あり!
※すでに知っている方や、関係ない方はスルーしてください。
BYDは本当に買う人いるの?売れない理由と評判の真相とは!?のまとめ
記事のポイントをまとめてます。
- 日本での販売台数は年間2,200台ほどと少ない
- 市場シェアはEV全体の約0.9%にとどまる
- 主な購入者は価格重視のEV初心者
- 環境意識の高い家庭がターゲット層に含まれる
- 在日中国人や中国系企業の購入も目立つ
- 長澤まさみ起用のCMで来店者は一時的に増加した
- 認知度向上と購入意欲の間にギャップがある
- トヨタと技術提携しているが市場では競合関係もある
- 日本のEV普及率は2〜3%と世界的に低水準
- BYDは価格とバッテリー性能で差別化を狙っている
- 走行性能や静粛性には一定の評価がある
- 内装やナビの使い勝手に課題があるとの声がある
- サポート体制やディーラー網が発展途上にある
- 故障率は他社EVと比べて大きな差はない
- ブレードバッテリーは耐熱性と安全性に優れる
- バッテリーは10年後でも90%以上の容量を維持する試験結果がある
- 急速充電の多用や過酷な環境での使用は劣化を早める
- 日本撤退の公式発表はなく、販売拠点は拡大中
- ブランドへの信頼感がまだ浸透していない
- デザインや価格への心理的な抵抗がある
- 修理対応や部品供給の不安を感じる人が多い
- 自宅充電ができない場合は不便が大きい
- 公共の充電設備が整っておらず外出時に不安が残る
- 初めてのEVやセカンドカーとしてはコスパが高い
- 購入前には試乗や他社との比較が重要である

管理人の車好きからの心からの一言
こんにちは、車好きの管理人です。最後まで読んでいただきありがとうございます。
正直なところ、私自身も「BYDって本当に買う人いるの?」と疑問に思っていた一人です。
でも、調べていくうちに、世界的にはすでに大手の一角を占めるメーカーであること、そして「価格と性能のバランス」で勝負していることに気づきました。
まだ日本では知名度もインフラもこれからですが、たとえば新しいレストランに初めて入るときのように、「ちょっと気になる存在」になってきているのは確かです。
もちろん、ブランド力やサポート体制に不安を感じる人も多いと思います。
けれど、EVという新しい時代のクルマ選びには、少しだけ“柔軟な視点”も大切だと感じます。
あなたにぴったりの「BYDの魅力」を見つけてみてください!
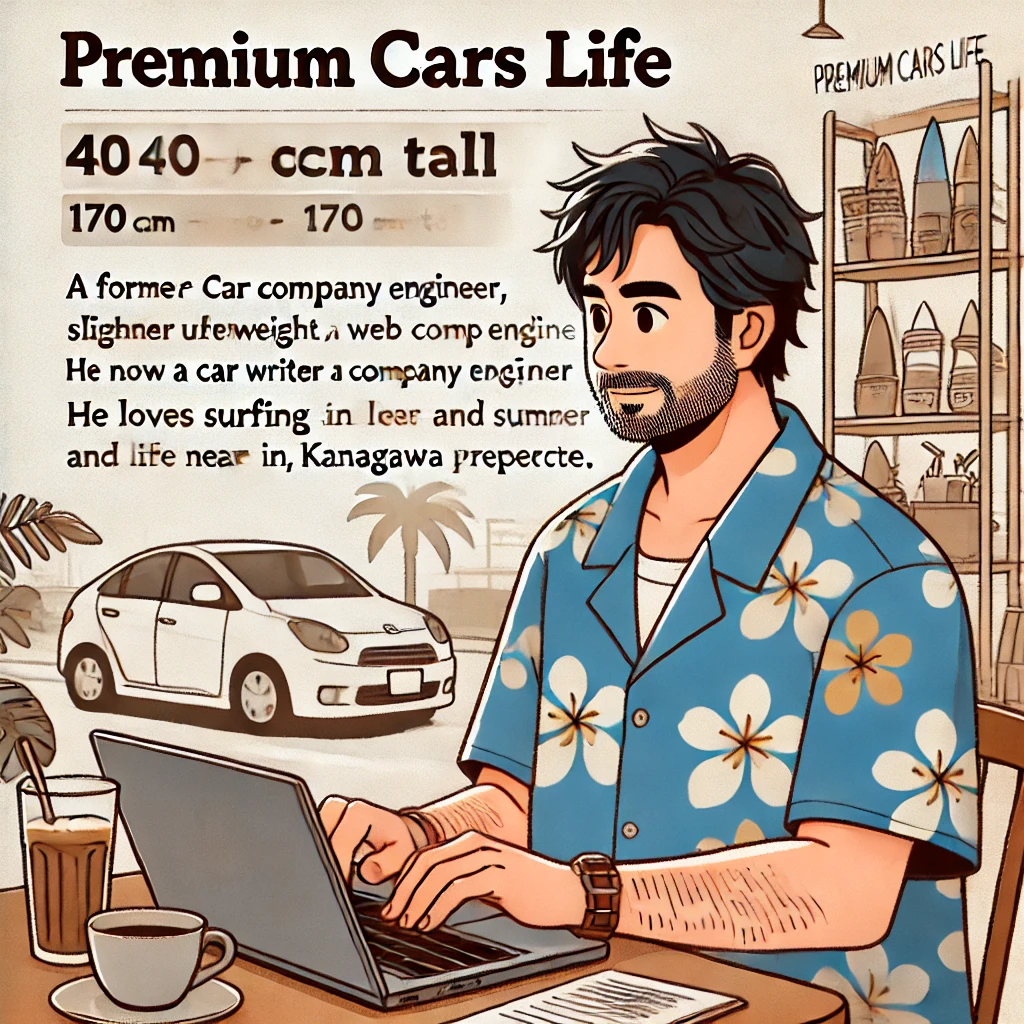
関連記事・参照リンク
